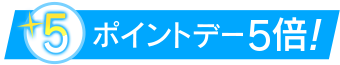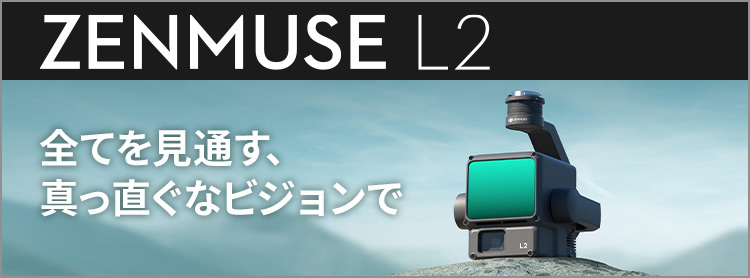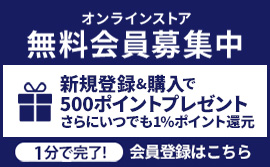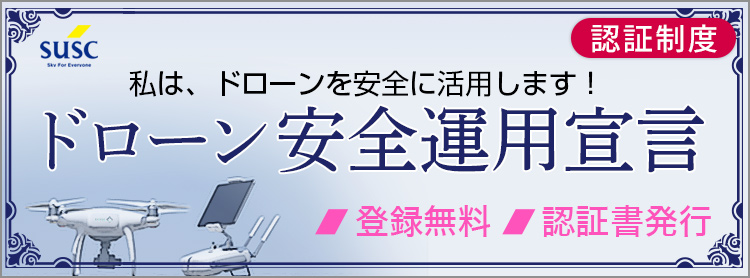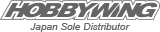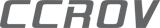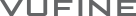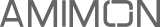ROV・水中ドローンによる船底点検の最新情報
こんにちは、セキドの高木です。
2021年12月9日に日本海事協会(NK・ClassNK)から発表された、遠隔操作が可能なROV・水中ドローンに関する性能や安全性に関する要件などをまとめた「ROV/AUVに関するガイドライン」に、セキドが協力した、船底検査へのROV・水中ドローン活用に関するトライアルが10ページに渡ってレポートされましたので、今回はそちらのトライアルの詳細をご紹介いたします。
※本記事の内容は公開時(2021年1月)の情報となります。現在提供可能な内容と異なる場合がございますのでご了承ください。

今回のトライアルにおけるドライドックの撮影比較などが詳細にレポートされている「ROV/AUVに関するガイドライン」は、発行元の日本海事協会ウェブサイトからダウンロードが可能です。
※「マイページ」中の「ガイドライン」に掲載されています。マイページの利用にはユーザー登録が必要となります。ダウンロード方法の詳細はこちらをご覧ください。
ガイドラインの概要
日本海事協会(NK・ClassNK)とは
日本海事協会(以後NK)が行う主な業務は、船舶の安全を確保するために制定した規則が、建造時と就航後の船舶に適用されていることを証明するための検査を実施することです。NKが制定する規則は、船体構造のみならず、推進機関、電気、電子システム、安全機器、揚貨装置など多岐に及びます。
国際船級協会としては世界最大の船級登録船(総トン)を誇ります。
ガイドライン発行の背景
船体・船底の検査ではNKが予め承認した場合、潜水士の代替手段として、ROV・水中ドローンによる水中検査の実施を認められています。
ガイドラインでは、革新的技術に関する安全基準の策定や第三者認証に関連する業界ニーズに応える活動の一環として、ROV・水中ドローンの運用における一般的に必要な機器や注意点、安全対策など基本的事項に関する内容がまとめられています。
BlueROV2 による船底検査への共同実証実験
検証概要と使用機材
船舶検査における潜水士の代替手段としてROV・水中ドローンによる運用を目指すため、性能および制度等の評価を行う検証を実施しました。
対象船は株式会社商船三井が運行する自動車運搬船「FLEXIEシリーズ」の4隻目にあたるDUGONG ACE(ジュゴン・エース)です。
船首部
バウスラスター、1W/2WS/2WPマーク、THR/1Wマーク+ボトムプラグ
船体中央部
ドラフトマーク、ビルジキール始端部
船尾部
ラダー(舵)検査用窓、プロペラブレード、シーチェスト
また、検証には BlueROV2 シリーズのうち、ベースモデルであるスタンダードを使用しました。

コントローラーとパソコン接続すれば、地上側は準備完了です。
オペレーションチーム構成は、ROV操縦士1名、ガイドおよび通信用テザーケーブルの介助者(作業員)1名の計2名で実施します。
検査対象の調査
プロペラやラダーが点在する船尾部を避け、船首側からROVを投入します。
水面へ投入は作業員1名で可能で、BlueROV2 本体を持ちながら通信用テザーケーブルを利用して手動吊り下げを行いました。
投入直後はケーブル介助者のガイドを頼りに、海面を船首部まで航行し、船外壁2m程度まで近づくとカメラによる視認が可能になりました。
それでは、実際に BlueROV2 で撮影した画像をご覧ください。
船首部・船体中央部
船尾部
船尾部はラダーやプロペラ等の設備により、通信用テザーケーブルが絡まないように、航行した分以上のケーブルは繰り出さないように注意をしました。
検査時の操縦
姿勢制御機能により、高い操縦技術は必要ありませんでした。今回は波により上下に揺れましたが、上下スラスターを増設したモデル「BlueROV2プロ(SBR200PR)」を使用することで解消されるでしょう。
大型船舶の場合は、1箇所に留まらず、調査ブロックごとに移動した方が運用が容易で、ケーブルの展開および巻取り作業を軽減させるリールがあると移動が効率的になります。
水中投入はテザーケーブルを使って吊り下げる形で対応し、通信用のテザーケーブルは高い強度を持つため、投入時に別途機材や設備を設ける必要はありません。
船体にROV本体が衝突した場合も、ROV本体のメインフレームは樹脂製であるため、船体に傷等をつける心配はありませんが、「セキドケア for ROV」などの保守サービスや保険があることでより安心して作業にあたることができます。
ROVでの撮影

ドラフトマークを撮影中のBlueROV2
カメラスタビライザー機能が十分に作動しており、揺れの少ない映像が撮影できました。
内蔵カメラでも調査点検に使用するに充分な画質でしたが、より高画質な Osmo Action や Insta360 ONE R などの外部カメラを取り付け撮影する事も可能です。
当日は多少の濁水環境下でしたが、対象に接近することで視認することができ、調査の問題にはなりませんでした。
まとめ
今回の実証トライアルでは、BlueROV2を使用した船底検査した場合の、撮影方法や必要な性能について確認することができました。操縦技能も充分に習得可能であり、ガイドライン中でも「オペレーターへの負荷も、ドローンと比較すると軽度で済むとの実感が得られたことから、オペレーターへの要件はドローンよりも軽減してもよいと考えられる」と考察されています。
船底点検に必要な ROV・水中ドローンは?
今回の検証結果から、船底点検を行う際に最適なROV・水中ドローンとして、下記の機種をオススメします。
QYSEA FIFISH V6 PLUS:価格はお見積り
4K動画撮影や測距ソナーによる離隔保持、レーザースケーラーによる採寸など船底点検に最適な機能が満載の最新水中ドローンです。特に湾曲する船体に対して、一定の距離を保ったまま航行出来るため、撮影品質の向上やオペレーターの負担軽減に繋がります。本体保守サービスに代わり、専用保険が用意されているため、故障や破損に対応することができます。
・ROV本体:FIFISH V6 PLUS 水中ドローン
※2023年1月現在、以下の機種は取り扱いを終了しています。
BlueRobotics BlueROV2 プロ(保守サービス付セット):税込 1,760,000円
BlueROV2 プロ 一式に加えて、可搬性が向上するケーブルリールや予備バッテリー、そしてROVの故障や破損に対応する保守サービスを組み合わせた導入が望ましいです。
・ROV本体 :BlueRobotics BlueROV2 プロ(保守サービス付セット)
・ケーブルリール:Fathom Spool Large[300m]
・バッテリー :BlueROV2 専用 4S 14.8V/ 18000mAh リチウムイオンバッテリー
セキドでは水中ドローンについてより詳しい情報や導入事例、実績などをお伝えする無料WEBセミナーも定期的に開催しており、具体的な用途やご検討中の課題についてのお問い合わせにも対応いたしますので、ぜひ一度ご参加ください。開催予定やお申込みはリンク先ページにてご確認ください。
今回のトライアルにも参加した経験豊富なスタッフが、お客様の用途や目的に合わせたROV・水中ドローンの選定・導入から運用までワンストップでご提供いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。

 お問い合わせ
お問い合わせ お買い物ガイド
お買い物ガイド ドローンガイド
ドローンガイド