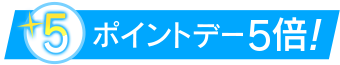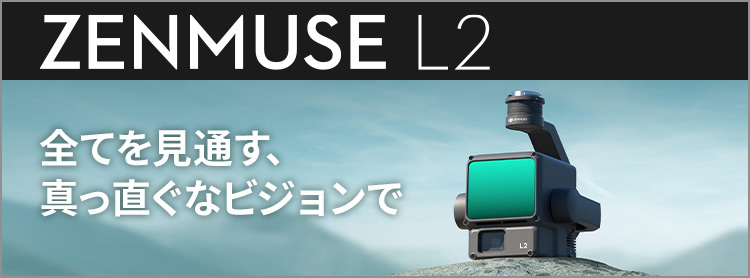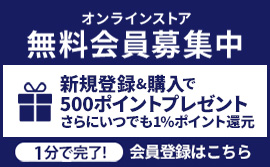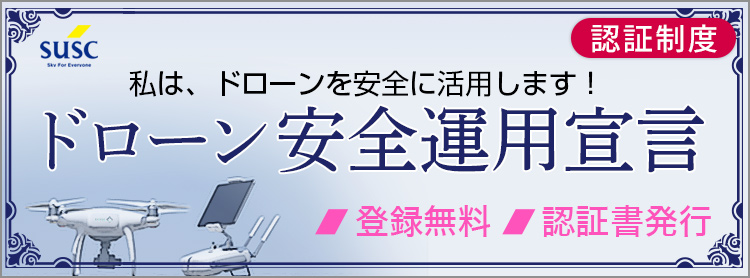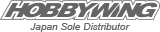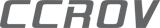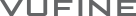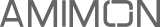こんにちは、セキドSUSC事務局の糸野です。
皆様、国土交通省航空局からドローンの事故事例が公表されていることはご存じでしょうか?
ドローンを飛行させていて事故を起こした場合、国土交通省に事故報告を行うこととされており、先日の衆議院で可決された改正航空法では、今後さらにこの点が強化される見込みとなっています。
国土交通省ではこの届け出られた報告をまとめ、定期的にウェブサイトで公開しています。
実際に公開されているPDFデータは下記のリンクをご覧ください。
平成30年度 無人航空機に係る事故トラブル等の一覧(国土交通省に報告のあったもの)
(PDF)
データが掲載されている「国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」ページはこちら
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
今回は、この事故事例を紐解きながら、ドローンで事故を起こさないための方法を学んでいきたいと思います。
1. 事故原因の集計
2. 知識不足・技量不足・確認不足など人に起因する事故
3. フライトプランの作成について
4. ドローン安全運用のすすめ
5. 業務としてのドローン安全運用について
1. 事故原因の集計

先に紹介した国土交通省発表による、事故トラブル等の一覧をもとに、下記の通り「事故原因」「飛行経験時間」について独自に集計いたしました。
| 知識不足・技量不足・確認不足など人に起因する事故 | 42 |
|---|---|
| 突風や砂埃等周辺環境に起因する事故 | 9 |
| バッテリ切れに起因する事故 | 4 |
| 送信機と機体の電波が途切れたことに起因する事故 | 8 |
| 自動操縦中に起きた事故 | 4 |
| 自動帰還機能中に起きた事故 | 3 |
| 経年劣化による部品の故障による事故 | 1 |
| 不正利用 | 1 |
| その他 | 7 |
事故原因の集計結果を見ると、「全体の半数以上が知識不足・技量不足・確認不足などに起因する事故」でした。
| 10時間未満 | 2 |
|---|---|
| 10時間以上 | 36 |
| 20時間以上 | 12 |
| 30時間以上 | 5 |
| 40時間以上 | 1 |
| 50時間以上 | 5 |
| 60時間以上 | 2 |
| 70時間以上 | 3 |
| 80時間以上 | 2 |
| 90時間以上 | 1 |
| 100時間以上 | 4 |
また、事故を起こした操縦者の経験時間としては、「10時間以上~30時間未満の操縦者が全体の66%以上」となっていました。
ただ、中には1,000時間以上のフライト経験のある操縦者が「対岸にある樹木と距離感が掴めなかったために接触してしまった」といった事例もあり、どれだけ飛行時間を積まれている方でも、油断により事故を起こすことがあります。
2. 知識不足・技量不足・確認不足など
人に起因する事故

次に、「事故原因」として最も多い「知識不足・技量不足・確認不足など人に起因する事故」の内訳にについて、下記の通り集計いたしました。
| 障害物をよく確認しなかったことに起因する事故 | 10 |
|---|---|
| 操作誤りによる事故 | 9 |
| 機体の整備不良やアプリの設定が誤っていたことに起因する事故 | 8 |
| GPSが途切れたことに起因する操縦ミスによる事故 | 6 |
| 送信機を注視していたことに起因する事故 | 4 |
| 機体を見失ったことに起因する事故 | 4 |
| 操縦者と補助者の連携不足に起因する事故 | 1 |
それでは、事故の詳細について回避策・予防策と合わせて確認していきましょう。
「電線や樹木などの障害物にあたってしまう事故」
こちらの事故は、事前の現場確認の不足により起きてしまう場合が多いようです。
回避策として考えられることは、ドローンをフライトさせる際は事前にフライトプランを必ず作成し、操縦者と補助者双方がフライトプランをしっかりと認識し、疑義がない状態で飛ばすことがあげられます。
実際に飛行させる際は必ず現場の状態を事前に確認し、フライトプランに矛盾がないか確認をするようにしましょう。
フライトを開始する時間の太陽の位置を考慮しておらず、実際にフライトさせようとしたら眩しくてフライトさせられなかった
などの事例もあります。
「操作誤りによる事故」
機体の向きを誤認したり、不用意な操縦をしていることが主因としてあげられます。
「整備不良やアプリの設定が誤っていたことに起因する事故」
整備不良・アプリの設定ミスについては、ルーティンとしてのフライト前の機体確認を怠ったがために、思わぬ事故に繋がることも多いようです。
「GPSが途切れたことに起因する事故」
「送信機を注視していたことに起因する事故」
初心者の方や操縦に慣れていない方が起こす事故として、非常にメジャーな事故で、SUSCの講習では、一番最初にこの事故についてお話しています。
業務でドローンを飛ばす際にこれらの事故を防ぐためには、普段からのたゆまぬ操縦訓練が必須なことはもちろん、実際のフライトの際にはカメラからの映像は補助者が確認し、操縦者は機体から決して目を離さない体制で運用するなどの工夫が必要です。
「送信機と機体の電波が途切れたことに起因する事故」
操縦者の知識不足からくる事故として非常に件数が多い事故です。日本は湿度が高いため元々電波が届きにくい環境で、それに加えてイベントや催し物上空など電波が混信しやすい状況や、遮蔽物などが多い見通しの悪い環境で飛ばすため、送信機と機体の電波が途切れてしまい機体を見失って事故に繋がる事が多いです。
そのような状態にならないよう、そもそも電波が混信しやすい環境での運用を控えることができれば一番ですが、しかたなくこのような状況で飛ばす場合は、万が一の事態に備えた安全対策をしっかり行うことが重要です。
電波が途切れた際に安全に機体を着陸させるためには、事前のアプリ設定が適切にされていることはもちろん、操縦者自身がしっかりとした知識を持ち、慌てずに事態に対処する必要があります。
「GPSが途切れたことに起因する操縦ミスによる事故」
GPSが一時的に使えなくなってしまう状況に対する対処も「機体と送信機の電波が途切れたことに起因する事故」と同様、普段からそのような状況に対応するための訓練を積むことで、いざという時に安全にドローンを着陸させることができます。
3. フライトプランの作成について

先程も事故に対する回避策で簡単に触れた「フライトプラン」についてですが、フライトプランを作ることで事故原因の大部分を回避することができます。
例えば、
「突風や砂埃等周辺環境に起因する事故」
については周辺環境を確認することや、フライト前の風速チェックを厳密に行うようフライトプラン作成するべきですし、
「バッテリ切れに起因する事故」
の大部分である、風の影響を受けバッテリが足りなかったなどの状況は、事前に作成したフライトプランでの考慮不足が原因です。
ドローンフライトにおけるフライトプランの作成はあらゆる事態を考慮し、万全の準備をするためのツールとして非常に重要です。
その分、フライトプランの作成には熟練の知識が必要で、経験の少ない操縦者や補助者ですとフライトプランの作成が未熟であったり、そもそも作成していないなどが原因で事故が起こることが大変多くなっています。
4. ドローン安全運用のすすめ

事故事例を紐解きつつ、具体的な対処方法などを解説してきましたが、実際の運用時にどれだけのリスクヘッジができるかは、最終的にはドローンパイロットや補助者の「知識・技量・経験」に依存してしまいます。
ただ、このようなドローンを安全に飛ばすためのノウハウやナレッジというものは、一朝一夕で身に付くものではなく、安全運用について一から必要な体制を構築しようとしても多くのコストが必要となります。
ドローンの安全運用について、必要な知識や技術を身につける必要性を感じられた方には、「SUSC(セキド無人航空機安全運用協議会)」が運営している国土交通省登録技能資格「SUSC 無人航空機操縦士 技能認定」がおすすめです。
国内No.1のドローン販売・取り扱い実績と、これまでに8000名を超える方に講習を行ってきた セキド・SUSC だからこそできるコストを抑えつつ提供する実践的な講習の中には、セキドが実業務を通じて得た安全運用のナレッジや、実際にドローンを業務に取り入れている企業から得たノウハウについても豊富に解説していますので、これから業務でドローンを飛ばしたい方には垂涎ものの内容となっております。
事故を未然に防いで業務効率を改善するため、ドローン講習を選択する一つのポイントとして、『安全運用』を一つのキーワードとしてみてはいかがでしょうか?
5.業務としてのドローン安全運用について
業務に利用されているドローンの安全運用について対策を検討されている方に向けて、セキドでは企業向けの特別講習会を実施しております。
お客様のニーズや課題に合わせたカリキュラムを作成しますので、無駄なく効率的にドローンの安全運用について身につけて頂くことが可能です。
ご相談、お見積もりのご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
セキド虎ノ門本店 産業用ドローン相談窓口
03-5843-7836(月~金 10:00~17:30)

 お問い合わせ
お問い合わせ お買い物ガイド
お買い物ガイド ドローンガイド
ドローンガイド